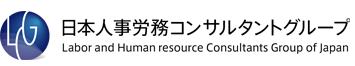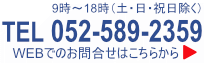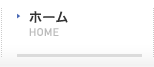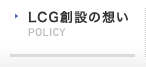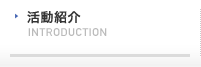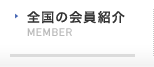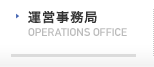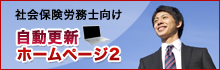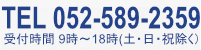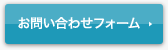社労士サミット2016 お申込みはこちら
※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-
【オープニングパネルディスカッション】 9:40-10:50
取捨選択の時代、社労士の強み、事務所の強み あなたは何を選ぶか?女性社労士の観点から
[パネラー]
諸星裕美氏(オフィスモロホシ 代表)
安中繫氏(ドリームサポート社会保険労務士法人 代表)
菊地加奈子氏(特定社会保険労務士 菊地加奈子事務所 代表)
[コーディネーター]
宮武貴美(社会保険労務私法人名南経営)
【分科会】
■A会場(大会議室)
[A1]11:00-12:00
手続き業務こそ社労士の価値!?
講師:安中繁氏(ドリームサポート社会保険労務士法人 代表)
1・2号業務は社労士だからこそできる仕事。しかし一方では手間隙かかる割には顧問先に貢献できている実感が少ないと嘆く方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回の講演では、手続業務を進める上での具体的なフローやミス回避の工夫、価値を高めるための提案方法・価格設定などをお伝えします。
①外注業者とは違う社労士ならではの1・2号業務の進め方
②効率化・ミス回避のための具体的アイデア
③プラスアルファの工夫 ~会社と従業員の絆を深めるお手伝い
[A2]13:00-14:00
いまだからこそ、必要とされる社労士像
講師:諸星裕美氏(オフィスモロホシ 代表)
社労士で初めて、国の機関である「社会保険審査会」の委員に任命された経験をもとに、年金部会、私学共済審査会、複数の厚生労働省委託事業に関わることができました。その中で、国の施策等に関し、現場・実務を知る社労士の必要性を肌で感じています。
労働法や社会保険に関わる法改正が続くこの時代だからこそ、社労士の活躍が益々求められる一方で、社労士としての本来の役割を忘れがちになっていないか、皆様に改めて考えていただく機会になれば、という想いで今回、社労士サミットに登壇します。いまや、社労士の認知度は上がり、社会だけでなく、行政側からもさらに必要とされている事実があることはもちろん、そのために社労士として何をすべきか、その心がけについても具体的にお伝えします。
①これからの社労士に求められる力とは?
・行政処分は法令に即していることを忘れずに
・実務と現場の視点を持った発信力を培う
・常に誰かに見られていることを意識する
・チャレンジ精神がなければ人脈は活かせない
②審議会、委託事業等の動向から
・各省庁の委託事業に、社労士はいまや必須アイテム
・現場の声を拾い上げ始めた行政等
・社労士が活躍できるヒントが動向情報の中に満載されている
[A3]14:10-15:10
デジタル社会の社労士ビジネス
講師:大野実氏(社会保険労務士法人大野事務所 代表)
「日本の人口ボーナス期」は1990年ごろに終わり、「人口オーナス期」=人口構成の変化が経済にとってマイナスに作用する時代・重荷・負担の時代に入りました。
一方、あらゆる機器をインターネットでつなげて制御するインターネット・オブ・シングス(IoT)の導入、人工知能やロボットの活用拡大の時代が到来し、産業の構造、工場や物流の現場、人の働き方を劇的に変えていく時代に突入しました。今、まさに「革命が津波のように押し寄せ、すべてのシステムを一変させる時代といえます。
社労士は、このような「未知の領域」むかって、どのように創造し挑戦していくべきなのかという視点で、お話させていただきます。
①激変する時代の予兆
②社会のデジタル化で変わるもの
③弁護士・税理士・社労士の現状
④デジタル社会の社労士ビジネス
⑤デジタル社会の「新たな事業」への展開
⑥まとめにかえて~未来の選択~
■B会場(201会議室)
[B1]11:00-12:00
残業ゼロの労務管理 実際にはなにを提案し、どう進めているの?
講師:望月建吾氏(社会保険労務士法人ビルドゥミー・コンサルティング 代表)
ヒトと組織の生産性をアップさせる究極の方法は、「残業をゼロにしても、それまで以上の生産性を上げる最強組織の仕組みづくりを行うこと」です。それを自社の企業体力に合わせてできる方法を1つでも2つでも見つけて、実際に手を動かしていくことに意味があり、そこに労務管理の「プロ」である社労士が介在し、実効性を高めていくことが重要でしょう。そのためには、”ナレッジ偏重”、”机上の空論”の”お客様に選ばれない”バーチャルな社労士像ではなく、「実践経験」と「組織力」に裏打ちされた「説得力」のある「選ばれる」リアルな社労士像を求道していかなくてはなりません。専門家としてお客様に相対する以上、事務所経営の成功は「義務」です!
今回の講演では、当社の残業ゼロの労務管理支援の成功事例はもちろん、企業への提案・導入手法、更には事務所経営を成功させる私の実践した経営戦略や商品開発、マーケティングの実践についても詳しく解説する予定です。
①小さな会社でも成功!業種別残業ゼロの労務管理支援の成功事例
②私の社労士としてのマインドセット~社労士としてのスタンスから事務所経営戦略まで~
③おかねもっちー流ゴールセッティングの技術
④人事コンサルサービスをどう売るか?
[B2]13:00-14:00
高品質のサービスを提供するための社労士事務所としての在り方
講師:内海正人氏(日本中央社会保険労務士事務所 代表)
社会保険労務士事務所としてよりお客様に質の高いサービスを提供するためには、「何が必要なのか?」「どんなことを求めればよいのか?」「どうやって提供すればよいのか?」といった点を中心に事務所サービスの在り方を見直していかなければなりません。今回の講演では、営業・実務の両面において押さえておくべきポイントをお話しすると共に、実務上盲点となり、実務上で大きな事故に繋がりかねない「意外と見落としがちな『知らなければいけない』項目」についてお伝えします。お客様をリードして、より質の高いサービスを提供するのに欠かせない情報ですので、是非持ち帰ってください。
①社労士事務所の営業・運用~事務所のサービスのコアを何にするのか
・経営資源は限られている
・事務所に対する将来のビジョンは
・職員に何を任せるのか
・サービスメニューの確立
・どうやって新規の獲得を行うのか
②実務上のポイント
・決算賞与制度導入時に落としてはいけない就業規則作成のポイント
・意外と知らない歩合給と割増賃金の関係とは
・年俸制における給与と賞与の考え方の整理
[B3]14:10-15:10
人材不足・少子高齢化・育児介護 働き方変革の必要性が高まる中、ますます求められる社労士になる方法
講師:菊地加奈子氏(特定社会保険労務士菊地加奈子事務所 代表)
今後ますます深刻化する人口減少・人口構成の大きな変化によって、日本企業は長きにわたって慣習化してきた雇用システムのあり方の大きな変革を迫られています。
女性の社会進出や男女平等といった視点や、配慮の下に整備されてきた仕事と家庭の両立支援策といったものでは到底太刀打ちできない深刻な問題に対し、明確かつ具体的な解を示すことができるのが社労士であり、今後ますますビジネスチャンスは広がっていくでしょう。
国が掲げていく施策に対し、法律・制度を熟知した専門家として、企業における人事制度改革・働き方の変革をサポートする存在になっていくために、どのような方法が考えられるのか。お客様企業に求められている社会的責任に対し、どのような助言を行えるのか。今回の講演では、国や行政とも連携しながら新たな働き方を実践し、その可能性を提言しているワーク・イノベーションの取り組み事例の紹介と共に解説します。
①企業の人材不足問題に対してますます重要になる社労士の存在
・女性活躍推進法が企業にもたらす「働き方変革」
・「配慮」だけではダメ!育児介護問題とこれからの両立支援策
・内部の人材育成がカギ。教育とキャリアパスのあり方
②ワーク・イノベーションで成長する企業に
・事業所内保育が担う役割と可能性
・テレワークの環境整備の必要性
・国や地域との連携
【クロージングパネルディスカッション】 15:20-16:30
電子政府と人材不足で社労士業界はこう変わる
~今後激変する環境とその中で求められる社労士の役割・サービスとは?
[パネラー]
大野実氏(社会保険労務士法人大野事務所 代表社員)
立岩優征氏(社会保険労務士法人日本人財化センター 代表社員)
小山邦彦氏(社会保険労務士法人名南経営 代表社員)
[コーディネーター]
大津章敬(社会保険労務士法人名南経営 代表社員)
マイナンバー制度もスタートし、いよいよ本格的な電子政府時代の扉が開かれました。今後、様々な分野での電子化が急速に進み、我々、社会保険労務士の業務も大きな変革が求められることになるでしょう。
一方で、労働力人口の減少による人材不足は深刻さを増しており、有効求人倍率は既にバブル経済期の水準に匹敵するレベルとなっています。従来は「ヒト・モノ・カネ」と言われましたが、今後は安定的な人材の確保ができる企業だけが勝ち残る「まずはヒト」の時代となっていきます。このように考えると、「ヒトと組織の専門家」である社会保険労務士の活躍の場はこれからますます拡大していくことでしょう。
今回のパネルディスカッションでは、社労士業界の電子化およびマイナンバーを牽引してきた先駆者をパネリストに迎え、これからの経営環境における社会保険労務士の役割と提供していくべきサービスについて議論していきます。
※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-
社労士サミット2016 お申込みはこちら